この記事では、そうしたAI時代に必須となる新しい検索最適化「AEO(Answer Engine Optimization)」の全貌を解説します。AEOの基本的な意味やSEOとの決定的な違い、そしてAIに選ばれるコンテンツを作るための具体的な6つの実践ステップまで、初心者にも分かりやすく解説しています。
結論から言えば、今後の検索対策で最も重要になるのは、ユーザーの質問に対し、AIが「信頼できる最適な答え」として認識できる情報を用意することです。ぜひチェックしてみて下さい。
BLOGFORCLEのブログ
AEO対策
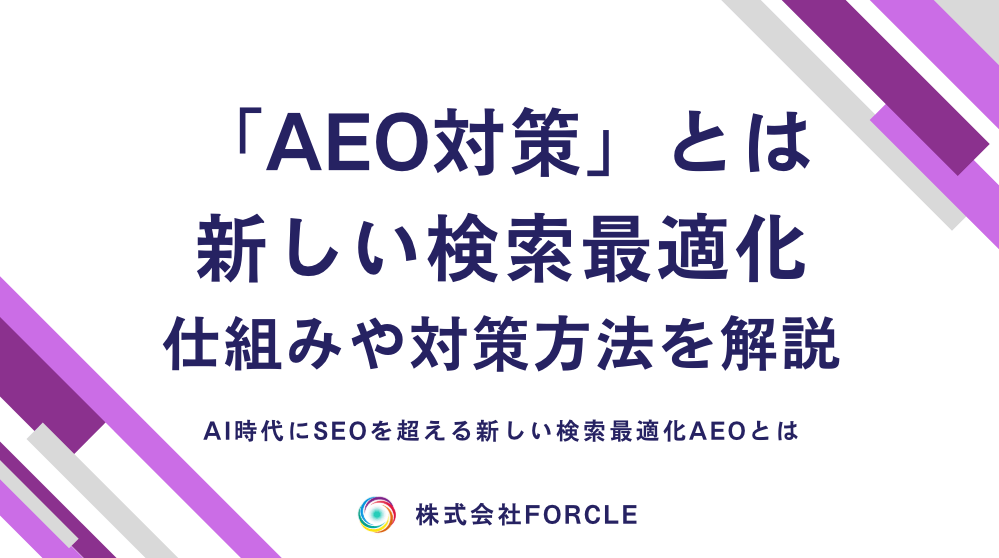
GoogleのSGE(Search Generative Experience)やChatGPTといった生成AIの登場で、検索の常識が大きく変わろうとしています。これまでのSEO対策だけを続けていては、AIが生成する回答に自社サイトが表示されなくなり、ビジネス機会を失うのではないかと考える方も少なくないでしょう。
この記事では、そうしたAI時代に必須となる新しい検索最適化「AEO(Answer Engine Optimization)」の全貌を解説します。AEOの基本的な意味やSEOとの決定的な違い、そしてAIに選ばれるコンテンツを作るための具体的な6つの実践ステップまで、初心者にも分かりやすく解説しています。
結論から言えば、今後の検索対策で最も重要になるのは、ユーザーの質問に対し、AIが「信頼できる最適な答え」として認識できる情報を用意することです。ぜひチェックしてみて下さい。
目次
近年、デジタルマーケティングの世界で「AEO対策」という新しい言葉を耳にする機会が増えてきました。これは、ChatGPTに代表される生成AIの台頭により、人々の情報収集の方法が大きく変わろうとしていることを背景にしています。従来のSEO対策だけでは、今後のAI時代を勝ち抜くことは難しくなるかもしれません。この章では、AEO対策の基本的な意味から、SEOとの具体的な違い、そして今なぜこれほどまでに注目されているのか、その理由を分かりやすく解説します。
AEOとは、「Answer Engine Optimization」の略称で、日本語では「回答エンジン最適化」と訳されます。これは、生成AIやAI搭載型検索エンジンがユーザーの質問に対して最適な回答を生成する際に、自社のウェブサイトやコンテンツを情報源として選んでもらうための最適化手法全般を指します。これまでのSEO(Search Engine Optimization:検索エンジン最適化)が、Googleなどの検索結果ページで自社サイトを上位に表示させることを目的としていたのに対し、AEOはAIによる「回答」そのものに自社の情報が組み込まれることを目指す、より進んだ概念です。ユーザーがAIと対話する中で、自社の製品やサービス、専門知識が自然な形で紹介されることで、新たな顧客接点を生み出すことが期待されています。
AEOという考え方が急速に広まった背景には、テクノロジーの劇的な進化があります。特に大きな影響を与えたのが、OpenAI社の「ChatGPT」やGoogle社の「Gemini」といった、高性能な対話型AIの普及です。これにより、ユーザーの検索行動は、単にキーワードを打ち込んで関連サイトのリストを得るというものから、AIに対して自然な言葉で質問し、要約されたダイレクトな答えを得るという形へと変化しつつあります。
この流れを決定づけたのが、Googleが導入した「SGE(Search Generative Experience:生成AIによる検索体験)」です。SGEは、検索結果の最上部にAIが生成した回答の概要を表示する機能であり、ユーザーはウェブサイトを一つひとつクリックしなくても、検索結果ページだけで疑問を解決できるケースが増えました。この「ゼロクリックサーチ」の増加は、従来のウェブサイトへのトラフィックを大きく減少させる可能性を秘めており、企業にとって見過ごせない変化です。このような検索体験の根本的な変革期において、AIに情報源として認識されるためのAEO対策が、ビジネスの存続に関わる重要な戦略として浮上してきたのです。
AEOとSEOは、どちらも検索における可視性を高めるという目的は共通していますが、その対象とアプローチが大きく異なります。SEOが「検索エンジン」を対象とするのに対し、AEOはAIという「回答エンジン」を対象とします。両者の違いを理解するために、以下の表で比較してみましょう。
| 項目 | SEO(検索エンジン最適化) | AEO(回答エンジン最適化) |
|---|---|---|
| 最適化の対象 | GoogleやYahoo!などの「検索エンジン」のアルゴリズム | SGEやChatGPT、Geminiなどの「回答エンジン(生成AI)」 |
| 主な目的 | 検索結果ページでの上位表示(ランキング向上) | AIが生成する回答の情報源としての引用・採用 |
| 重視される要素 | キーワード含有率、被リンクの質と量、サイトの表示速度など | 情報の正確性、E-E-A-T(経験・専門性・権威性・信頼性)、構造化データ、明確なQ&A形式 |
| ユーザーの行動 | 検索結果のリンクをクリックし、サイトを訪問して情報を探す | AIが生成した回答を読み、疑問を解決する(引用元へのアクセスは二次的) |
| コンテンツの評価軸 | キーワードとの関連性、網羅性、ユーザーの滞在時間など | 質問に対する直接的で簡潔な回答、事実に基づいた客観的な情報 |
このように、SEOがウェブサイトへの「集客」を主な目的とするのに対し、AEOはAIを介した「情報発信」に重点を置いています。重要なのは、AEOはSEOを完全に置き換えるものではないという点です。AIはウェブ上の膨大な情報を学習データとしており、その情報収集の基盤には従来の検索エンジンの技術が使われています。したがって、良質なコンテンツ作成やE-E-A-Tの向上といったSEOの基本は、AEOにおいても同様に重要です。これからの時代は、従来のSEO対策を土台としながら、AIに正しく情報を解釈・引用してもらうためのAEOという新たな視点を加えていくことが求められます。
従来のSEO対策だけでは通用しない時代が訪れようとしています。その背景には、GoogleやOpenAIといった巨大テック企業が主導する、生成AI技術の急速な進化があります。ここでは、なぜ今AEO対策に取り組むべきなのか、その理由を具体的な動向から分析します。
AEO対策の重要性を理解する上で、まず知っておくべきなのがGoogleが試験導入を進めている「SGE(Search Generative Experience)」です。SGEは、検索結果にAIが生成した要約を表示する新しい検索体験を指します。
これまでの検索結果は、ユーザーが入力したキーワードに対して関連性の高いWebページのリスト(青いリンク)が表示されるのが一般的でした。しかしSGEが導入されると、検索結果の最上部にAIによる回答(AIスナップショット)が提示され、その下に従来の検索結果が続く形に変わります。
ユーザーは、複数のサイトを巡ることなく、AIがまとめた回答だけで疑問を解決できる場面が増えるでしょう。これは、Webサイト運営者にとって、AIの回答に自社の情報が引用されるかどうかが、ユーザーに情報を届けるための最初の関門になることを意味します。SGEの登場は、検索の常識を大きく変え、AIに選ばれるための最適化、すなわちAEO対策の必要性を強く示唆しているのです。
AEOが求められる理由は、Googleの動向だけにとどまりません。OpenAIの「ChatGPT」やGoogleの「Gemini」に代表される対話型AIサービスの普及も、大きな要因の一つです。
多くのユーザーが、情報収集やアイデア出しのツールとして、従来の検索エンジンと並行して、あるいはそれ以上にAIチャットを利用し始めています。この動きは、人々が情報を得るための「入り口」が多様化していることを示しています。
以下の表は、従来の検索とAI回答型検索の主な違いをまとめたものです。
| 項目 | 従来の検索エンジン(Googleなど) | AI回答型検索(ChatGPTなど) |
|---|---|---|
| インターフェース | キーワード入力型の検索窓 | 自然な文章での対話形式 |
| 情報の提示方法 | Webページのリンク一覧 | 要約・整理された直接的な回答 |
| ユーザーの行動 | 複数のサイトを訪問・比較検討 | 回答を元に追加で質問・深掘り |
これらのAIも、Web上に存在する膨大な情報を学習データとして回答を生成しています。つまり、自社のWebサイトが持つ情報がAIにとって信頼性が高く、引用しやすい形で存在していれば、Google検索以外の場所でもユーザーにリーチできる可能性が生まれます。AEO対策は、検索エンジンの枠を超え、あらゆる「回答エンジン」に向けた情報発信の最適化といえるでしょう。
SGEやAIチャットの普及は、ユーザーの検索行動そのものを変え、結果としてビジネスにも大きな影響を及ぼします。
まず予測されるのが、検索クエリの変化です。「渋谷 カフェ」といった単語の羅列ではなく、「渋谷駅の近くで、打ち合わせに使える静かなカフェはありますか?」のように、より具体的で話し言葉に近い、長い質問形式の検索が増加するでしょう。
また、「ゼロクリックサーチ」の増加も懸念されます。これは、AIが生成した回答だけでユーザーが満足し、Webサイトを一切クリックすることなく検索を終えてしまう現象です。これにより、これまでSEO対策で獲得してきたWebサイトへの自然検索トラフィックが減少する可能性があります。
こうした変化は、ビジネスに次のような影響をもたらします。
これまでの「Webサイトへの集客」を前提としたマーケティング戦略だけでは、AI時代に生まれる新たなビジネス機会を逃してしまうかもしれません。未来のユーザー行動に対応し、AIという新しい情報チャネルで選ばれる存在になるために、今からAEO対策に着手することが極めて重要です。
これからの検索体験では、ユーザーが入力した質問に対し、AIが最適な答えを生成して提示する形式が主流となっていきます。この大きな変化に対応するためには、従来のSEO対策の考え方をアップデートし、AIに「良質な情報源」として認識され、回答に引用してもらうための「AEO対策」が重要です。ここでは、AI時代の検索エンジンに評価されるコンテンツを作成するための、6つの具体的な実践ステップを解説します。どれも明日から取り組める実践的な内容ですので、ぜひ自社サイトのコンテンツ戦略にお役立てください。
AIはユーザーの質問(クエリ)に対して、最も的確な回答をウェブ上の情報から探し出し、生成します。そのため、コンテンツを「質問」と「回答」のセットで明確に提示するQ&A形式で設計することが、AEO対策の第一歩となります。
具体的には、見出しを「AEO対策とは?」のような質問形式にしたり、記事内に「よくある質問(FAQ)」セクションを設けたりする方法が有効です。コンテンツを作成する際は、まずユーザーが抱えるであろう疑問を想定し、その答えを簡潔に提示することから始めましょう。最初に結論を述べ、その後に理由や具体例を続ける「PREP法」を意識すると、人とAIの双方にとって理解しやすい構成になります。一つの見出し(質問)に対して一つの明確な答えを用意し、情報を整理することで、AIがコンテンツの内容を正確に把握し、回答として引用しやすくなります。
生成AIは、情報の正確性と信頼性を重視します。ウェブ上に溢れる二次情報や三次情報をまとめただけの内容では、他のサイトとの差別化が難しく、AIからの高い評価を得ることはできません。そこで重要になるのが、自社独自の調査や経験に基づく「一次情報」の発信です。
例えば、自社で実施した市場調査のデータ、顧客へのアンケート結果、独自の実験で得られた知見、具体的な導入事例などは、他にはない価値を持つ一次情報です。こうしたオリジナルの情報をコンテンツに盛り込むことで、情報の信頼性が高まり、AIが参照すべき重要な情報源として認識される可能性が高まります。情報を発信する際は、調査の概要やデータの根拠を明記し、その情報の正しさを裏付けることが大切です。一次情報の発信は、自社の専門性や権威性をアピールする上でも大きな武器となります。
E-E-A-Tは、Googleがコンテンツの品質を評価するために用いる重要な指針であり、この考え方はAEO対策においても変わりません。AIは、E-E-A-Tの高いサイトから優先的に情報を引用する傾向があります。特に、人々の幸福、健康、経済的安定、安全に影響を与える可能性のあるYMYL(Your Money or Your Life)領域のテーマでは、その重要性が一層高まります。サイト全体でE-E-A-Tを高め、ユーザーとAIの両方から信頼される情報発信を心がけましょう。
| 要素 | 概要 | 具体的な強化策 |
|---|---|---|
| Experience(経験) | コンテンツの作成者が、そのトピックについてどの程度の直接的な経験を持っているか。 | 製品の実際の使用レビュー、サービスの体験談、イベントへの参加レポートなど、実体験に基づいた内容を盛り込む。 |
| Expertise(専門性) | トピックに関する専門的な知識やスキルを有しているか。 | 特定の分野に特化したコンテンツを継続的に発信する。専門用語には丁寧な解説を加える。 |
| Authoritativeness(権威性) | その分野における第一人者、または情報源として広く認知されているか。 | 著者情報を明記し、経歴や資格、実績を示す。公的機関や業界団体からの言及、専門メディアへの掲載実績をアピールする。 |
| Trustworthiness(信頼性) | 情報が正確で、サイト全体が信頼できるか。 | 運営者情報を明確に記載する。プライバシーポリシーや問い合わせフォームを設置する。サイトをSSL化(HTTPS)する。 |
スキーマ(構造化データ)とは、HTMLに特定の情報を付加することで、検索エンジンにコンテンツの内容をより正確に、かつ効率的に伝えるための記述方法です。人間が見た目ですぐに理解できる情報でも、検索エンジンにはそれが何なのか正確に伝わらない場合があります。スキーママークアップを実装することで、「これはFAQです」「この人物が著者です」といった情報をAIに明確に伝えることができます。
AEO対策において特に有効なスキーマには、以下のようなものがあります。
これらの構造化データを適切に実装することで、AIがコンテンツの文脈を深く理解し、回答を生成する際の引用精度が高まります。
AI検索の普及に伴い、ユーザーの検索クエリは従来の単語の羅列から、より会話に近い「自然言語」へと変化していきます。「渋谷 ランチ おすすめ」のようなキーワード検索だけでなく、「渋谷で一人でも入りやすいランチのお店は?」といった話し言葉での検索が増加するでしょう。また、スマートスピーカーの普及により、音声による検索も一般化していきます。
この変化に対応するためには、ユーザーが実際に口にするような自然な疑問文を想定し、それに答えるコンテンツを作成することが求められます。タイトルや見出しに具体的な質問を取り入れたり、平易で分かりやすい言葉遣いを心がけたりすることが有効です。特に「なぜ?」「どうやって?」「何が必要?」といった、5W1Hを含む質問への回答を網羅することで、多様な検索意図に応えることができ、AIに選ばれる可能性が高まります。
AIは、コンテンツ単体の品質だけでなく、その情報が掲載されているウェブサイト全体の信頼性も評価します。サイトの信頼性を測る指標として、従来からSEOで重要視されてきた「被リンク」や、オンライン上での「評判(サイテーション)」が、AEO対策においても引き続き重要な役割を果たします。
関連性が高く権威あるサイトからの被リンクは、自社サイトが信頼できる情報源であることの証となります。また、SNSやレビューサイト、他のブログなどで自社のブランド名やサービス名が好意的に言及されることも、サイトの信頼性を高める上で大きなプラスとなります。Googleビジネスプロフィールをはじめとする各種プラットフォームでの情報を整備し、ユーザーからの良い口コミを増やすといった地道な活動が、巡り巡ってAIからの評価を高めることにつながるのです。コンテンツ作りと並行して、サイト全体の信頼性を高める取り組みも進めていきましょう。
AEO対策を成功させる上で、従来のキーワード選定と同じくらい、あるいはそれ以上に重要となるのが「質問設計」です。生成AIはユーザーから投げかけられた「質問」に対し、最も的確な「回答」をウェブ上の情報から探し出し、再構成して提示します。つまり、自社のコンテンツをAIに回答の一部として選んでもらうためには、AIが理解しやすく、かつユーザーの疑問に直接答える「質問と回答」のセットをコンテンツ内にあらかじめ用意しておくことが極めて重要になるのです。これは、検索キーワードの裏にあるユーザーの検索意図を、より深く読み解き、先回りして回答を用意する作業とも言えるでしょう。
生成AIが回答を生成する際、参照するコンテンツには一定の傾向が見られます。AIが解釈しやすく、回答の根拠として引用しやすいコンテンツは、以下のような特徴を持つ質問形式を含んでいます。
コンテンツを作成する際は、これらの点を意識し、AIが「これは良質な質問と回答のペアだ」と認識できるような形式を心掛けることが、AEO対策の第一歩となります。
ユーザーが抱く疑問の多くは、「5W1H(いつ・どこで・誰が・何を・なぜ・どのように)」で整理できます。これらの要素をコンテンツに盛り込むことで、ユーザーの多様な検索意図を網羅し、AIにとっても文脈を理解しやすい情報となります。コンテンツの企画段階で、テーマに対して5W1Hの視点から質問を洗い出し、それぞれに回答を用意するアプローチは非常に有効です。
具体的な質問設計の例を以下の表に示します。
| 疑問詞 | 質問設計の例 | コンテンツ作成のポイント |
|---|---|---|
| What(何を) | AEO対策とは何か? | 用語の定義や目的、基本的な概念を誰にでも分かる言葉で丁寧に説明します。 |
| Why(なぜ) | なぜ今、AEO対策が必要なのか? | SGEの登場や検索行動の変化といった背景を解説し、対策をしない場合のリスクやメリットを明確に伝えます。 |
| Who(誰が) | AEO対策は誰が担当すべきか? | 企業のマーケティング担当者、Web担当者、コンテンツ制作者など、対象となる読者を具体的に示します。 |
| How(どうやって) | AEO対策は具体的にどうやって進めるのか? | 具体的な手順や手法をステップ形式で解説します。専門的な内容も、図や例を交えて分かりやすく説明することが求められます。 |
| When(いつ) | AEO対策はいつから始めるべきか? | SGEの本格導入前など、対策を始めるべきタイミングや、その根拠を示します。 |
| Where(どこで) | AEO対策の情報はどこで確認できるか? | Googleの公式発表や信頼できる専門メディアなど、情報の参照元となる場所を具体的に挙げます。 |
このように、5W1Hを軸に質問を設計することで、情報の網羅性が高まり、ユーザーが抱くであろうあらゆる角度からの疑問に答えることができます。
FAQ(よくある質問)の形式は、AEO対策において非常に強力な手法です。質問と回答が明確にペアになっているため、AIがユーザーの疑問に対する直接的な答えとして認識しやすくなります。質の高いFAQコンテンツを作成するためのポイントは以下の通りです。
これらのポイントを押さえてFAQコンテンツを作成し、さらに後述する構造化データを適切に実装することで、AIが自社サイトの情報を「信頼できる回答」として引用する可能性を大幅に高めることができるでしょう。
AEO対策を進める上で、多くの方が抱く疑問についてQ&A形式で解説します。新しい概念であるため、基本的な疑問から具体的な実践方法まで、ここで解消していきましょう。
AEO対策とAIO対策は、どちらもAIに関連する用語ですが、その目的と範囲が異なります。AEOは「Answer Engine Optimization(回答エンジン最適化)」の略で、AIが生成する回答の引用元として自社コンテンツが選ばれることを目指す施策です。一方、AIOは「AI Optimization」の略で、AI技術をマーケティング活動全般に活用し、最適化することを指します。AEOは、広義のAIOの中に含まれる一つの施策と捉えることができます。
両者の違いを以下の表にまとめました。
| 項目 | AEO対策(回答エンジン最適化) | AIO対策(AI最適化) |
|---|---|---|
| 目的 | 生成AI(SGEなど)の回答に自社コンテンツを引用・表示させること | AI技術を活用してマーケティング活動全体の効果を最大化すること |
| 対象領域 | コンテンツマーケティング、SEO、Webサイトの信頼性向上 | コンテンツ生成、広告運用、顧客データ分析、市場予測など多岐にわたる |
| 具体的な手法 |
|
|
| 目指すゴール | AI検索におけるオーガニックな露出と権威性の確立 | 業務効率化とマーケティングROI(投資対効果)の向上 |
結論から言うと、中小企業にこそAEO対策は重要であり、大きなチャンスとなり得ます。大企業が網羅しきれないニッチな領域や、地域に密着した専門的な情報において、AIから高く評価される可能性があるからです。
従来のSEOでは、広告予算やドメインの強さで大企業が有利になる側面がありました。しかしAEOでは、ユーザーの具体的な質問に対して、最も的確で信頼性の高い回答を持つコンテンツが評価されます。そのため、特定の分野や地域に特化した質問に対して、中小企業ならではの深い専門知識や経験に基づいたコンテンツが回答として選ばれやすくなります。
例えば、「〇〇市でおすすめの工務店の選び方」といった地域性の高い質問や、「〇〇(専門的な製品)のメンテナンス方法」といったニッチな質問に対して、質の高いコンテンツを用意することで、AI検索結果の上位に表示される可能性が十分にあります。これは、新たな顧客獲得やブランド認知の向上に直結する重要な戦略です。
AIに回答の引用元として選ばれやすくするためには、いくつかの重要なコツがあります。これらは従来のSEOの考え方を踏襲しつつ、AIの特性を理解した上で実践することが大切です。
AIはユーザーの質問に対して、迅速かつ的確な回答を生成しようとします。そのため、コンテンツの冒頭で質問に対する結論を明確に示し、その後に理由や具体例を解説する「結論ファースト」の構成が効果的です。ユーザーが求める答えに素早くたどり着ける構成は、AIにとっても評価しやすい形式です。
他のウェブサイトの情報をまとめただけのリライトコンテンツは、AIから評価されにくくなります。自社独自の調査データ、顧客へのインタビュー、専門家としての見解など、オリジナリティのある一次情報を盛り込むことで、コンテンツの価値は飛躍的に高まります。AIは情報の独自性や信頼性を判断基準の一つとしているため、他にはないユニークな情報の発信を心がけましょう。
AIは常に最新の情報を学習しています。そのため、公開したコンテンツを定期的に見直し、情報が古くなっていないかを確認する作業が重要です。特に統計データや法律、製品情報などは、最新の情報に更新し、更新日を明記することで、コンテンツの鮮度と信頼性をアピールできます。
本記事では、AI時代の新しい検索最適化であるAEO対策について、その概要から具体的な実践方法までを解説しました。GoogleのSGEやChatGPTといった生成AIの急速な普及により、ユーザーの情報収集の方法は「キーワードで調べる」から「AIに質問して答えを得る」形へと大きく変化しつつあります。
このような検索行動の変化に対応し、自社の情報がAIに選ばれ、ユーザーに回答として提示されるためには、従来のSEO対策の考え方をさらに発展させたAEOの視点が不可欠です。AEO対策はSEO対策と全く異なるものではなく、むしろE-E-A-Tといった信頼性の基盤の上に成り立つものです。
明確なQ&A形式のコンテンツ作成、一次情報の発信、構造化データの実装といったAEO対策は、AIがコンテンツの内容を正確に理解し、信頼できる情報源として認識するために極めて重要です。検索のあり方が変わる過渡期である今、いち早くAEO対策に着手することが、将来のビジネスにおける大きなアドバンテージとなるでしょう。ぜひ本記事で紹介したステップを参考に、AIに選ばれるコンテンツ作りを始めてみてください。