BLOGFORCLEのブログ
家具・インテリア雑貨ECの市場動向は?現状と課題、トレンドについて
EC業界
- 2025年11月9日
- 2025年10月26日

家具EC市場は成長を続けており、新規参入や事業拡大を検討している方も多いでしょう。
しかし、市場の具体的な規模や今後の動向、成功のポイントが分からず、戦略立案に悩むケースも少なくありません。
本記事では、最新のデータを基に家具・インテリア雑貨ECの市場規模の推移とEC化率を詳しく解説します。
【家具・インテリア業界のリスティング広告】平均クリック単価や運用戦略を解説
目次
拡大を続ける日本の家具EC市場規模

近年、私たちのライフスタイルの変化に伴い、家具やインテリア雑貨をオンラインで購入する消費行動が一般的になりました。特に、在宅時間の増加はEC市場の成長を大きく後押ししています。
最新データで見る市場規模の推移
経済産業省が発表した「電子商取引に関する市場調査」によると、「生活雑貨、家具、インテリア」分野のBtoC-EC(消費者向け電子商取引)市場規模は、堅調な成長を続けています。
コロナ禍でいわゆる「巣ごもり需要」が急増した2020年以降もその勢いは衰えず、市場は拡大基調にあります。
| 年 | 市場規模 | 前年比 |
|---|---|---|
| 2020年 | 2兆1,324億円 | +21.5% |
| 2021年 | 2兆2,752億円 | +6.7% |
| 2022年 | 2兆2,768億円 | +0.07% |
2020年に前年比20%を超える大幅な成長を記録した後、2021年、2022年もプラス成長を維持しています。2022年は微増となりましたが、これはコロナ禍の反動減が見られる分野もある中で、高水準の市場規模を維持していることを示しています。
消費者の購買行動として、家具やインテリアのオンライン購入が完全に定着したと言えるでしょう。
家具分野のEC化率と今後の予測
EC化率とは、すべての商取引のうち、EC(電子商取引)が占める割合を示す指標です。この数値を見ることで、その分野でどれだけオンラインでの購入が浸透しているかが分かります。
「生活雑貨、家具、インテリア」分野のEC化率は、他の物販分野と比較しても高い水準で推移しており、年々上昇傾向にあります。
| 年 | EC化率(生活雑貨、家具、インテリア) | EC化率(物販系分野全体) |
|---|---|---|
| 2020年 | 26.03% | 8.08% |
| 2021年 | 28.25% | 8.78% |
| 2022年 | 29.59% | 9.13% |
2022年には29.59%に達し、物販系分野全体の平均(9.13%)を大きく上回っています。この背景には、小物雑貨などECと相性の良い商品がカテゴリ内に含まれていることもありますが、従来は実店舗での購入が主流だった大型家具においても、オンライン販売が着実に拡大していることがうかがえます。
家具ECの市場規模が拡大している背景
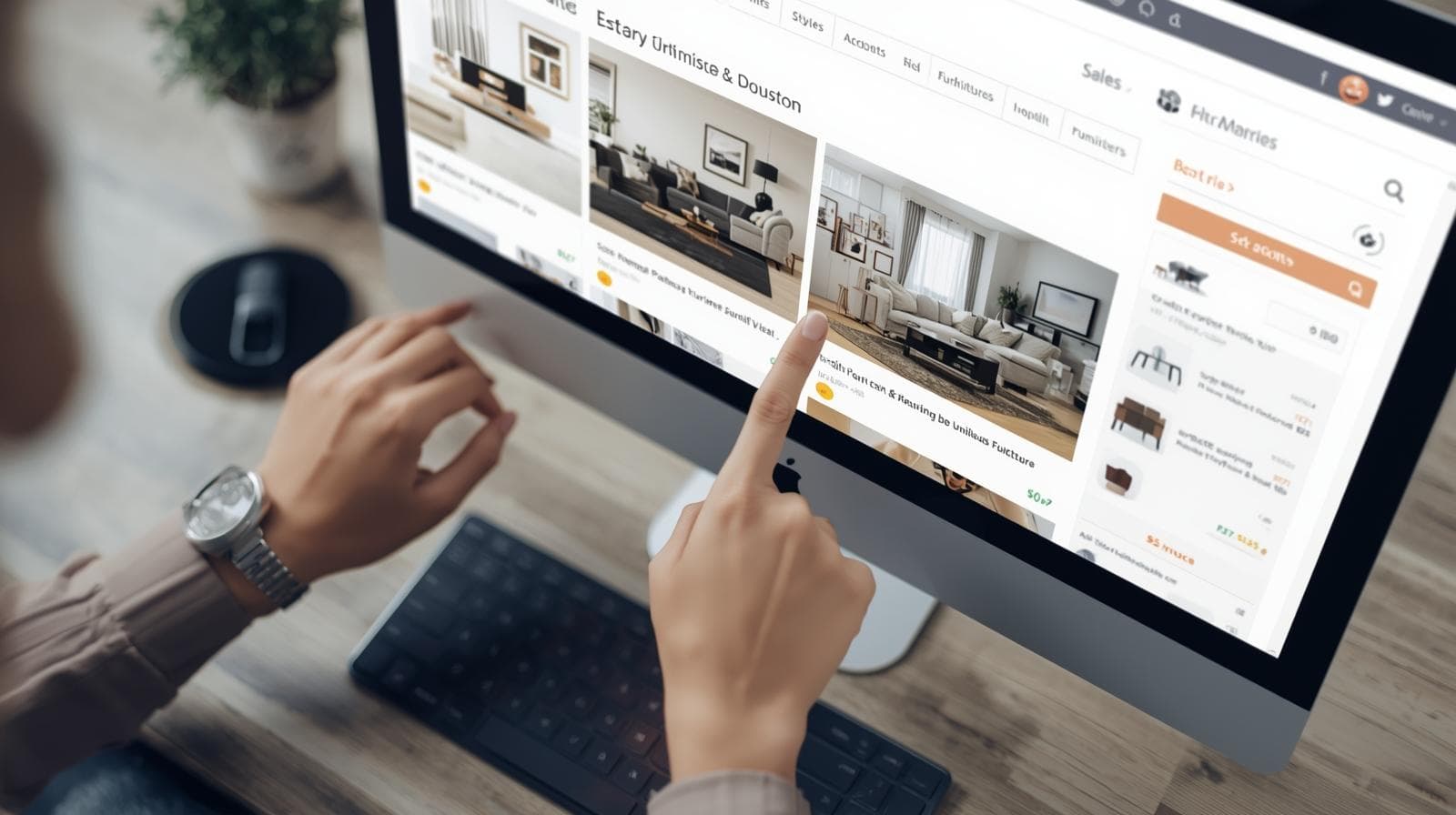
家具ECの市場規模は、なぜこれほどまでに成長を続けているのでしょうか。その背景には、単一の要因だけでなく、社会情勢の変化、テクノロジーの進化、そして新しいビジネスモデルの登場が複雑に絡み合っています。
コロナ禍で定着した新しいライフスタイル
新型コロナウイルス感染症の拡大は、私たちの生活様式に大きな変化をもたらしました。
特に、在宅時間の増加は家具・インテリアへの関心を一気に高めるきっかけとなりました。これまで以上に自宅の快適性を重視する人が増え、ECサイトでの家具購入を力強く後押ししています。
| ライフスタイルの変化 | 具体的な家具・インテリア需要 |
|---|---|
| 在宅勤務・リモートワークの定着 | 仕事に集中できるワークデスクや、長時間の作業でも疲れにくいオフィスチェア、書類や機材を整理するための収納家具など、ホームオフィス環境を整えるための需要が急増しました。 |
| 外出自粛による「巣ごもり需要」 | 自宅で過ごす時間が増えたことで、リビングでくつろぐためのソファやローテーブル、家族で食卓を囲むダイニングセット、質の高い睡眠を求めるベッドや寝具など、居住空間全体の質を向上させるアイテムへの投資が活発になりました。 |
| 「おうち時間」の充実 | 映画鑑賞や読書、オンライン飲み会など、自宅での余暇活動をより楽しむためのニーズが高まりました。大型テレビに対応するテレビボードや、部屋の雰囲気を変える照明器具、空間を彩るインテリア雑貨などの需要が伸びています。 |
ARやVRなど購入を後押しする技術の進化
かつて家具ECの大きな障壁とされていたのが、「実物を確認できない」という点でした。
サイズ感や色合い、部屋の雰囲気との相性などが分からず、購入をためらう消費者は少なくありませんでした。しかし現在では、AR(拡張現実)やVR(仮想現実)といった最新技術がこの課題を解決しつつあります。
代表的な技術として、以下のようなものが挙げられます。
- AR(拡張現実)による「試し置き」機能
スマートフォンのカメラを使い、画面越しに実寸大の3D家具データを自分の部屋に配置できる機能です。これにより、購入前にサイズが合うか、他の家具とのバランスはどうかといった点を確認できます。ニトリやLOWYA(ロウヤ)などの大手ECサイトでも導入が進んでおり、オンライン購入の不安を大幅に軽減しています。 - 3Dビューワー・シミュレーター
商品を360度あらゆる角度から確認できる機能です。素材の質感や細部のデザインまで、まるで手にとって見ているかのようにチェックできます。また、複数の商品を組み合わせて部屋全体のコーディネートをシミュレーションできるサービスも登場し、より具体的なイメージを持って商品を選べるようになりました。
テクノロジーの力でオンラインショッピングのデメリットが解消され、高額な家具でも安心して購入できる環境が整いつつあることが、市場の成長を加速させています。
D2Cブランドの台頭による市場の活性化
D2C(Direct to Consumer)とは、メーカーが卸売業者や小売店を介さず、自社のECサイトなどを通じて消費者に直接商品を販売するビジネスモデルです。このD2Cモデルを採用する新しい家具ブランドの台頭が、市場全体の活性化につながっています。
D2Cブランドには、次のような特徴があります。
- 中間マージンの削減による高いコストパフォーマンス
流通にかかる中間コストを削減できるため、高品質な素材やデザイン性の高い商品を、比較的リーズナブルな価格で販売できます。 - SNSを活用した顧客との直接的な関係構築
InstagramやPinterestといったビジュアル重視のSNSとの親和性が高く、ブランドの世界観やストーリーを消費者に直接伝えることで、強いエンゲージメントを築きます。顧客の声をダイレクトに商品開発やサービス改善に活かせる点も強みです。
家具EC事業者が直面する3つの大きな課題
家具EC市場は成長を続けていますが、その裏で事業者は多くの課題に直面しています。市場の成長性だけを見て参入すると、思わぬ壁にぶつかる可能性があります。ここでは、特に重要となる3つの課題について詳しく解説します
課題1 物流コストの高騰と配送問題
家具EC事業において、最も経営に直結する課題の一つが物流です。家具はサイズが大きく重量もあるため、一般的な商品と比べて配送コストが格段に高くなります。近年では、この問題がさらに深刻化しています。
その背景には、燃料費の上昇や、いわゆる「2024年問題」に代表されるようなトラックドライバー不足があります。これにより、運送会社からの配送料金の値上げ要請が相次いでおり、物流コストの上昇はEC事業者の利益を直接圧迫する大きな要因となっています。
課題2 実物を確認できないことによる購入の壁
家具は、長期間使用する高額な商品です。そのため、多くの消費者は購入前に実物を見て、触れて、確かめたいと考えています。ソファの座り心地、テーブルの天板の質感、収納家具の引き出しの滑らかさなど、オンラインの情報だけでは伝わりきらない要素が購入の決め手となることも少なくありません。
実物を見られないというECの根本的な弱点は、特に家具という商材において大きな購入の壁となります。Webサイト上の写真や説明文をどれだけ充実させても、「イメージと違ったらどうしよう」という顧客の不安を完全に払拭することは困難です。
【家具EC向け】売れる商品画像の作成テクニック!効果的な撮影と加工方法
課題3 競合との差別化と集客戦略
市場規模の拡大は、同時に参入企業の増加を意味し、競争の激化を招きます。現在の家具EC市場には、ニトリや無印良品といった実店舗を持つ大手から、LOWYA(ロウヤ)のようなEC専業の有力プレイヤー、さらには独自のコンセプトを掲げる小規模なD2Cブランドまで、多種多様な競合がひしめき合っています。
このような状況下で新規参入したり、売上を伸ばしたりするためには、自社の強みを明確にし、ターゲット顧客に的確にアプローチする戦略が欠かせません。しかし、多くの事業者が価格競争に陥りがちです。大手企業のような規模の経済を働かせることが難しい中小事業者にとって、安易な価格競争は消耗戦となり、事業の継続を困難にします。
また、集客面でも課題は山積みです。SEO対策、Web広告、SNSマーケティング、インフルエンサーの活用など、集客チャネルは多様化・複雑化しています。限られた予算の中でどの手法を選択し、効果を最大化するかを見極めるのは容易ではありません。単に商品を並べるだけでは顧客の目に留まることすら難しく、ブランドの世界観を伝え、ファンを獲得していくための継続的な情報発信とコミュニケーションが重要になっています。
2025年以降の家具EC市場を読み解く5つのトレンド
EC化の波に乗り、拡大を続ける家具・インテリア市場ですが、消費者の価値観やテクノロジーの進化に伴い、その姿は常に変化しています。ここでは、2025年以降の市場動向を予測する上で重要となる5つのトレンドを詳しく解説します。
トレンド1 AR技術を活用したバーチャルな試し置き
家具ECにおける最大の障壁の一つが、「実物を自宅に置いた際のイメージが湧きにくい」という点です。サイズが合うか、部屋の雰囲気と調和するかといった不安は、購入をためらわせる大きな要因となります。この課題を解決する技術として、AR(拡張現実)の活用が急速に広がっています。
AR技術を使えば、スマートフォンのカメラを通して、実寸大の3D家具データを自分の部屋に仮想的に配置できます。これにより、利用者は購入前にサイズ感や色合い、他の家具との相性をリアルに確認でき、「思っていたのと違った」という購入後のミスマッチを大幅に減らすことが可能です。
トレンド2 サステナビリティを重視した商品開発と販売
SDGs(持続可能な開発目標)への関心の高まりは、消費者の購買行動にも大きな影響を与えています。特に、長く使い続ける家具においては、製品の背景にあるストーリーや企業の姿勢を重視する「エシカル消費」の傾向が強まっています。
企業の環境や社会に対する姿勢が、ブランドイメージを形成し、消費者の共感を呼ぶ重要な要素となっています。サステナビリティへの取り組みを積極的に情報発信することが、新たな顧客層の獲得に繋がります。
トレンド3 家具のサブスクリプションサービスの普及
「所有から利用へ」という消費スタイルの変化は、家具業界にも大きな変革をもたらしています。特に、転勤や引っ越し、ライフステージの変化が多い現代において、高価な家具を「所有」することのリスクを避けたいと考える層が増えています。そこで注目されているのが、家具のサブスクリプション(サブスク)サービスです。
CLAS(クラス)やsubsclife(サブスクライフ)といった専門サービスが市場を牽引しており、家具は「買う」ものから「利用する」ものへという新しい価値観が、今後さらに浸透していくでしょう。
トレンド4 AIによるパーソナライズされた顧客体験の提供
数万点もの商品が並ぶ大規模なECサイトでは、顧客が自分の好みに合った商品を効率的に見つけ出すことは容易ではありません。そこで、AI(人工知能)を活用し、顧客一人ひとりに最適化された購買体験を作り出す「パーソナライゼーション」が重要性を増しています。
AIは、顧客の閲覧履歴や購買データ、お気に入り登録などの行動データを分析し、その人の好みを学習します。
AIによるパーソナライズは、顧客の「探す」手間を省き、偶然の出会いを創出することで、ECサイト全体の利便性と満足度を飛躍的に向上させます。
トレンド5 オンラインとオフラインを融合したOMO戦略
EC市場が拡大する一方で、家具という高価格帯で長く使う商材においては、「実物を見て、触って確かめたい」というオフライン(実店舗)ならではのニーズも根強く残っています。このオンラインとオフラインの垣根を取り払い、双方の利点を最大限に活かすのがOMO(Online Merges with Offline)戦略です。
OMOでは、オンライン(ECサイト)とオフライン(実店舗)を分断されたチャネルとして捉えるのではなく、一連の顧客体験として設計します。これにより、顧客は自身の都合に合わせて、両者を自由に行き来できるようになります。
| 取り組み | 顧客が得られる体験 |
|---|---|
| ショールーミングストア | 店舗で商品の質感やサイズ感を確認し、ECサイトのQRコードを読み取って自宅に配送。手ぶらで買い物を楽しめる。 |
| オンライン接客 | 自宅にいながら、店舗の専門スタッフにビデオ通話でコーディネートの相談や商品説明を受けられる。 |
| 店舗受け取りサービス | ECサイトで注文した商品を、好きなタイミングで最寄りの店舗で受け取れる。送料の節約や確実な受け取りが可能。 |
| 顧客データの一元管理 | 店舗とECサイトで購買履歴やポイントが統合され、どちらを利用しても一貫したサービスを受けられる。 |
まとめ
今回の記事では家具・インテリアECの市場動向を解説しました。
コロナ禍を契機としたライフスタイルの変化や、ARといった新しい技術の登場が市場の成長を後押ししている一方で、事業者にとっては物流コストの高騰や競合との差別化といった大きな課題が存在します。
これらの課題を乗り越え、今後も成長が見込まれる市場で成功を収めるためには、ARによるバーチャルな試し置きや、AIを活用したパーソナライズ提案、オンラインとオフラインを融合したOMO戦略など、新しい顧客体験を生み出す取り組みが不可欠です。
国内の家具EC大手が実施しているように最新のトレンドを的確に捉え、自社の強みを活かした戦略を立てることが、これからの家具EC市場で勝ち抜くための鍵を握っていると言えるでしょう。
家具ECの売上改善については”株式会社FORCLE”におまかせ!
この記事を書いた人
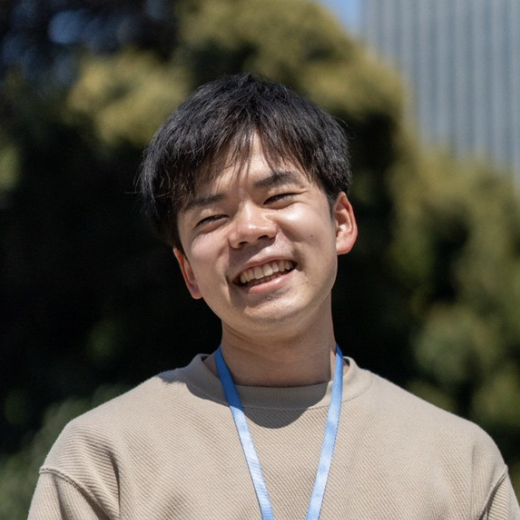
平井 和貴
株式会社FORCLE 平井です。デジタルマーケティング業界5年以上。メインはリスティング広告、ディスプレイ広告、Google Analytics分析、MEO対策を担当しております。WEBデザインの勉強中。。。

